|
ここでは金管楽器に使われている金属を挙げて、その特徴を説明していきます。
まず最も多様されているのが「真鍮(黄銅)」です。 真鍮は銅と亜鉛の合金で、軟らかいのが特徴です。 柔らかく、加工しやすいというの金管楽器の複雑な形状を成型するには不可欠な特徴です。 ですが真鍮の中にも様々な種類があり、微妙に特徴が異なります。
表の中にある「引張り強さ」というのは、 「値が大きければ大きいほど、その金属を引きちぎるのに必要な力が大きい」事を意味しています。 ですからイエローブラスとレッドブラスに同じように引っ張る力を増やしていくと、 レッドブラスの方が先に引きちぎれてしまうのです。 ところが金属の性質は引っ張り強さだけでは表せません。 そこで、上の表と対応した金属の特性を表すグラフを以下に示します。
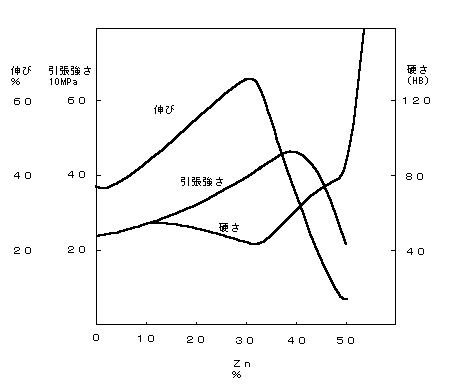
真鍮の機械的性質 (注:0〜10%の「引張り強さ」と「硬さ」のグラフは重複しているのであって、分岐しているわけではありません) ちょっとグラフがややこしいですが、あまり難しく考えずに気楽に読んで下さい。 複雑なグラフの見方はその値を読むことよりも、グラフの曲線の形が重要なのです。 さて、まずは「引張り強さ」のグラフを見てみると、亜鉛40%の時が最大で、 それ以上亜鉛を入れても引張り強さはの値は大きくなりません。 料理に入れる塩を増やせばどんどん塩辛くなりますが、合金の場合は 「ある金属を増やしつづけても、ある性質が常に増え続けるとは限らない」のです。 これはどんな合金でも共通する話です。 さて、金属の性質は「引張り強さ」だけでは表せません。 ここで「硬さ」のグラフが絡んできます。 「硬さ」は字の如く、「金属は木よりも硬い」というように、金属の硬度を表すものです。 また、「引張り強さと硬さは相反する」ものです。 グラフを見ると、「引っ張り強さ」の値が大きくなると「硬さ」の値は小さくなっています。 柔らかいものは引っ張ってもちぎれにくく、硬いものはちぎれやすい。 何か身近な物で経験した事があるのではないでしょうか? 同じように「伸び」もそのままの意味で、金属の伸びやすさを表しています。 この値が大きいと、金属は小さな力で引き伸ばすことができます。 「引き伸ばす」ということは「引張り」に深く関わるので、「引張り強さ」と同じようなグラフになります。 これは上のグラフを見ても同じようなグラフになっていることが分かりますね。 逆に値が小さいと金属は大きな力を加えないと伸びにくく、また無理に伸ばせばちぎれてしまいます。
では、これら3つの特徴を考え、イエローブラスとレッドブラスを比較してみましょう。
・イエローブラスは引張り強さの値は大きいですが、硬さの値は小さいです。しかもよく伸びます。 この性質は何を表しているのでしょうか? これは「イエローブラスは加工しやすく、レッドブラスは加工しにくい」事を表しています。 引張ってもちぎれにくく、伸びやすくて柔らかいイエローブラスは簡単に成型できます。 ところが、レッドブラスはちぎれやすく、伸びにくく、硬いので、成型をするのは容易ではありません。 イエローブラスを使うと、簡単に、そして安価に楽器を作ることができるのです。 ではなぜ、わざわざ成型しにくいレッドブラスを用いて楽器を作るのでしょうか? それはレッドブラスの特徴、「硬さ」のためです。 この硬さがイエローブラスとは異なる音色、レスポンスを出してくれるのです。 ですが加工しにくいことには変わりないので、一般には楽器のベル等の一部にレッドブラスが使用されている場合が多いです。 以下にそれぞれの真鍮ので作った楽器の特性を挙げておきます。
ただし注意しなければならないのが、 「音色は個人によって感じ方が違うので、表現が異なってくる」 事です。 これは抜粋した雑誌PIPERSの記事にも書かれていました。 つまり、誰もが上の表のような音に感じるとは限らないのです。
真鍮の次に金管楽器に多く用いられているのが洋白です。 洋白は真鍮(レッドブラス)よりも硬いのが特徴です。 またレッドブラスと同様、加工が困難なので抜き差し管のストレート部に用いられています。 抜粋したPIPERSには洋白の音色の特徴が書かれていませんでしたが、 これは洋白だけで作られた金管楽器がないためだと思われます。 以下に種類と合金の比率を挙げておきます。
|